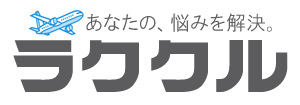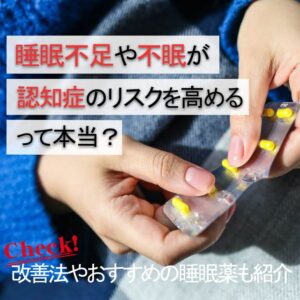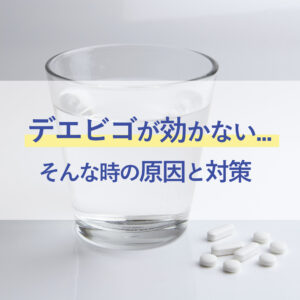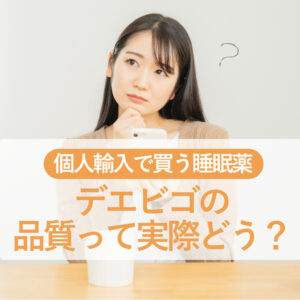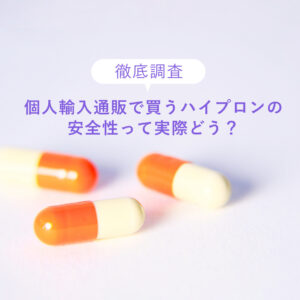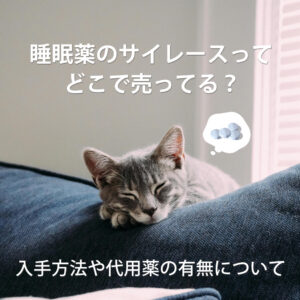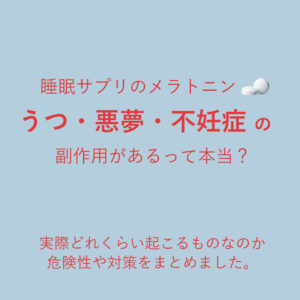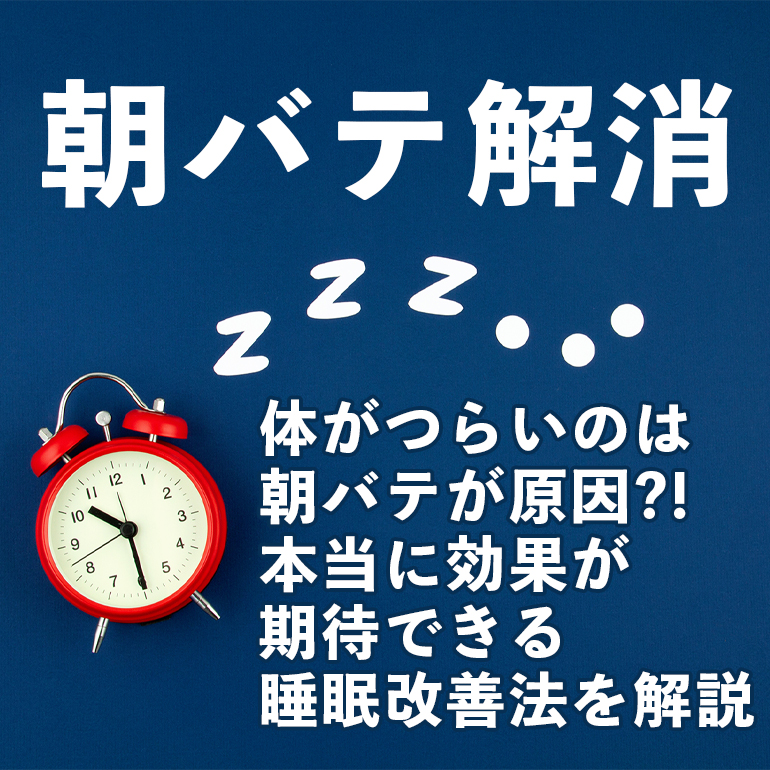
みなさんは朝起きてからの体の状態に満足されていますか。
「起きてから体がダルくてつらい」「寝たはずなのに疲れが取れていない」このような方は、朝バテが起きている可能性があります。
朝バテには睡眠の質が深く関係しているため、今回は朝バテの原因や睡眠改善法などを解説していきます。
朝バテとはどんな状態?
朝バテとは、睡眠の質の低下によって、翌朝になっても疲れが残ってしまっている状態を指します。
睡眠が浅かったり、夜中に何度も目が覚めたり、睡眠時間が短かったりすると日中の疲労が取れず、翌朝になってもダルさや倦怠感、疲労感などが残ってしまいます。
睡眠の質が低下する原因は様々ですが、主に眠りが浅い、睡眠時間の不足、睡眠リズムの乱れなどがあります。
以下に当てはまる方は、朝バテが起こっている可能性が高いです。
・ダルくてなかなか起きられない
・目覚ましが鳴ってもすぐ起きられない
・2度寝、3度寝してしまう
・起きた時が一番疲れている
・夜中に必ず目が覚める
・起きた時に体の痛みを感じる
朝バテになってしまう様々な原因
睡眠の質の低下によって起こる朝バテには、様々な原因があります「十分寝たはずなのに朝から疲れてる」「朝が一番しんどい」という方は以下で解説する睡眠の質低下の原因に当てはまるものがないかを確認してみてください。
ストレスや生活習慣、ホルモンバランスの乱れ、加齢について解説していきます。
ストレスや不安が原因の場合
日常生活でのストレスや心配事など緊張状態が続いていると、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目覚めてしまったりと睡眠の質に大きく影響します。
ストレスがあるとコルチゾールというストレスホルモンが過剰に分泌され、深い眠りを妨げます。
コルチゾールは副腎皮質から分泌されるホルモンの一種で、ストレスを受けると急激に分泌が増えるのですが、これはストレスから身を守ろうとして起きる現象です。
健康な状態ではコルチゾールの分泌量は朝にピークを迎え、就寝時に最も低くなりますが、ストレス状態が続いていると、このコルチゾール分泌リズムが乱れてしまいます。
ストレスが原因で夜になってもコルチゾール分泌量が減らず、脳が興奮状態に保たれてしまい眠りにくくなってしまいます。
慢性的な睡眠不足が原因の場合
みなさんは、日ごろから十分な睡眠をとることができていますか。
慢性的な睡眠不足が原因で睡眠の質が低下してしまい、朝バテや心身の不調につながることがあります。
2021年のOECD(経済協力開発機構) の調査報告 では、日本人の平均睡眠時間は調査対象33ヵ国の中でも最も短いとの報告もあります。
仕事や育児、介護、家事など、現代人は慌ただしく忙しい毎日を送っているため、十分な睡眠を確保できていない方が多くいます。
生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、成人の適正な睡眠時間の目安として6~8時間としています。
しかし、これには個人差があり、例えばロングスリーパーの人は無理に睡眠時間を減らしてしまうとかえって睡眠不足を招いてしまう可能性があります。
6~8時間の睡眠時間はあくまで目安として参考にしましょう。
重要なポイントは、自身にとって十分な睡眠時間を確保し、睡眠の質を下げないことです。
出典:OECD Gender Data – PortalOECD(経済協力開発機構) の調査報告(xlsx)アルコールが原因の場合
寝つきを良くするためにアルコールを飲む方もいるかと思いますが、アルコールは睡眠の質を下げる原因の一つと言われています。
たしかにアルコールを摂取ることによって、寝つきが良くなることがあるかもしれませんが、覚醒しやすくなり、深い睡眠を阻害してしまいます。
また、就寝前のアルコール摂取が日常的になると、量が増えていき、ますます深い睡眠をとることが難しくなってしまいます。
アルコールは体内に入った後、2~3時間後に代謝されますが、その途中でアセトアルデヒドという物質が生成されます。
このアセトアルデヒドには覚醒作用があるほか、二日酔いの原因ともなる物質です。
加えてアルコールには利尿作用もあるため尿意で目が覚めてしまい、深い睡眠を阻害してしまいます。
アルコールを摂取する場合は、目安として就寝の3時間前までにするといいといわれていますが、体調やアルコール度数によって分解にかかる時間は変わるため、心配な方は飲酒を避けた方がよいでしょう。
厚生労働省では「節度ある適度な飲酒」として1日平均純アルコール20g程度としています。
純アルコール20gを、お酒ごとに換算すると以下になります。
・ビール(5%) 500ml
・ウイスキーダブル(43%) 60ml
・チューハイ(7%) 350ml
・日本酒(15%) 1合弱
・ワイン(12%) 200ml
・焼酎(25%) 100ml
カフェインが原因の場合
コーヒーが好きでよく飲んでいるという方も少なくないかと思います。しかしカフェインの摂り過ぎや摂取する時間によって、睡眠の質を低下させてしまっている可能性があります。
またコーヒーだけでなく、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどにもカフェインが含まれているため注意が必要です。
カフェインは、眠気を引き起こすアデノシンという物質の働きを阻害することで、眠気が抑えられ、覚醒状態をもたらします。
カフェインの効果には個人差があり、カフェインを摂取した後の血中濃度は30分~2時間程度で最大となり、その後2~8時間で半減期を迎えます。
カフェインを日常的に摂取している方は、夕方以降の摂取は控えることをおすすめします。
農林水産省や海外の食品安全機構が示す1日摂取量の目安については健康な成人の場合約400mgまで、妊婦中の場合200mgになります。
・ドリップコーヒー60mg / 100ml
・インスタントコーヒー1杯当たり80mg
・玉露160 mg / 100ml
・せん茶20 mg / 100ml
・ほうじ茶20 mg / 100 ml
・紅茶30 mg / 100 ml
ホルモンバランスの乱れが原因の場合
ホルモンバランスの乱れは、特に女性に多く見られ、睡眠の質に深く関わりがあります。
生理前はプロゲステロン(黄体ホルモン) が多量に分泌されるのですが、これが日中の眠気や睡眠障害の原因といわれています。
ホルモンバランスはストレスによって崩れやすく、ストレスフルな毎日が続いていると脳内のホルモンや神経伝達物質に異常をきたし不眠症状が現れることがあります。
また女性の場合、更年期障害の症状の一つとして不眠が現れる場合があります。
更年期の不眠の原因は、女性ホルモンの分泌量低下による自律神経の乱れと考えられています。
更年期障害の一つであるホットフラッシュ(ほてりと発汗) が夜間に何度も起こることによって熟睡ができず、不眠になってしまうことがあります。
加齢が原因の場合
加齢による体内時計の変化によって、血圧、体温、ホルモン分泌などの生体機能リズムが前倒しになるため、高齢者は若者よりも早寝早起きになる傾向があります。
加齢とともに体力が低下し、日中の活動量が低下することにより体力を消耗しないため夜間の睡眠時間が短くなります。
また睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量も加齢とともに減少していくため、睡眠の質の低下や不眠の原因となります。
朝バテの原因は病気が関係している可能性もある
朝からダルい、疲れている場合、それは病気を患っている可能性があります。
病気に早く気づき、早めの治療を行うことで睡眠の質を改善にも繋がるため、思い当たる節がある場合は、早めに医療機関に受診しましょう。
以下では、睡眠の質を低下させる病気を解説していきます。
睡眠時無呼吸症候群が原因の場合
睡眠中に何度も息が止まってしまう睡眠時無呼吸症候群も睡眠の質を低下させる原因のひとつです。
平均して1時間に5回以上、10秒以上息が止まる状態であると睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
睡眠中に呼吸が停止してしまうことで眠りの質が悪くなり、日中の眠気や倦怠感・疲労感などの症状を引き起こします。
また血液中の酸素が欠乏することによって、脳、心臓、血管に負担がかかってしまい、脳卒中、心筋梗塞、狭心症などの重篤な合併症になる可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群患者は、肥満、飲酒習慣がある、中高年がなりやすいとされています。
出典:厚生労働省 – 睡眠時無呼吸症候群 / SASうつ病などの精神疾患が原因の場合
うつ病などの精神疾患を患っている場合、夜中に目が覚めることが多く、再び眠りにつくことが難しいことがあります。
また寝つきが悪かったり、早朝覚醒、悪夢を見るという事例もあるため、睡眠の質が低くなってしまいます。
うつ病などの精神疾患による睡眠障害がみられる場合は、適切な治療が必要なため早めに医療機関へ相談しましょう。
以下に当てはまる人はうつ病の可能性があります。
・精神的ストレスが多い(職場環境、対人関係、残業などで過労、家庭問題、介護問題、教育問題など)
・憂うつな気分が続いている
・何に対しても興味や喜びが起きない
・疲れやすく、やる気が起きない
・休日は動けず、寝ていることが多い
・対人関係で気を遣いすぎる
・寝付けない、途中覚醒、早朝覚醒が多い
朝バテ解消には寝だめがいい?!
仕事がある平日は決まった時間に起きるけど、休日は疲れた体を癒すためにいつもより遅い時間に起きるということはないでしょうか。
このような行為を「寝だめ」といいますが、平日と休日の生活リズムがずれてしまうと、わたしたちの体内時計を狂わせてしまう原因となります。
ある程度、遅く起きることで体の疲れを癒すことはできますが、寝すぎには注意が必要です。
平日と休日の就寝・起床リズムがずれてしまうと体内時計が乱れてしまい、時差ぼけのようになってしまいます。
これをソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ) といいます。
私たち人間にもともと備わっている体内時計は、睡眠、覚醒、ホルモン分泌、体温など、体の基本的な機能をコントロールしています。
朝起きて、日光を浴びることで体内時計はリセットされ、規則正しい生活によって正常に機能します。
しかし、休日は午後まで寝ているなどといった過度な寝だめをすることによって、日光を浴びるタイミングが遅れてしまい、体内時計が後ろにずれてしまいます。
ずれてしまった状態で、休日明けに平日の起床時間に戻すと、体は時差ぼけ状態となり、不眠、眠気、倦怠感、集中力低下などの症状が出ます。
睡眠の質低下の原因の一つにこのソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ) も関係しているのです。
寝だめをする時は睡眠中央値を意識する
「明日は休みだから、普段よりも2時間多く寝よう」「今週はハードだったから休みの日は4時間多く寝ていたい」仕事をしていると、このようなことが多くあるかと思います。
しかし、休みだからといっていつもより夜更かしして、起きる時間も午後まで寝ているなんてことをしていたら、簡単に体内時計がくるってしまいます。
体内時計が乱れることが原因でソーシャル・ジェットラグになってしまうことは前章で解説した通りです。
寝だめをする時は、睡眠中央値を意識することが大切です。
睡眠中央値とは、眠りに落ちた時間と起床時間のちょうど中間の時間のことを指します。
例えば、就寝時間が午前12時で起床時間が6時の場合、睡眠時間は6時間で睡眠中央値は午前3時になります。
この睡眠中央値を毎日揃えて睡眠のリズムを整えることが重要となるので、休日にいつもより2時間多く寝たいという場合は、午後11時に就寝して起床時間を7時とすると、睡眠時間が8時間で睡眠中央値が3時となるので、普段の睡眠中央値とずれることがありません。
仮に休日前だからといって夜更かしをして午前2時に就寝して10時に起床すると、睡眠中央値が午前6時となってしまい、普段よりも3時間のずれが生じてしまいソーシャル・ジェットラグになってしまいます。
睡眠中央値は2時間以上ずれないように心がけることで、睡眠のリズムが崩れにくくなり、睡眠の質低下を防止するために役立ちます。
寝だめについての研究
一昔前まで寝だめは効果がないといわれてきましたが、近年は寝だめの効果・可能性について様々な研究がされています。
その一例として2018年にスウェーデンのストックホルム大学が行った研究では、平日の睡眠時間が短くても週末の睡眠時間が中程度または長い人の死亡率は常に7時間睡眠を確保していた人と変わらなかったという報告があります。
この研究から寝だめには一定の効果があることが考えられますが、あくまで暫定的な結論に過ぎないため、これからも寝だめに関する研究から目が離せません。
出典:Sleep duration and mortality – Does weekend sleep matter?すぐできる! 本当に効果が期待できる睡眠改善法
朝から辛い朝バテを解消するためには良い睡眠をとり、睡眠の質を高めていくことが重要です。
普段何気なく行っている習慣が睡眠の質を低下させてしまっている可能性があるため、ここではすぐに始められる良い睡眠をとるための睡眠改善法を解説していきます。
照明と室温
蛍光灯や電子機器などのブルーライトなど、夜間の強い光は睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。
そのため夜間の室内は暖色系の照明や間接照明などを使用し、できるだけ目や脳に刺激の少ない環境をつくっていきましょう。
ポイントは寝室だけでなく、リビングやダイニングなど部屋全体を暖色系にし、できるだけ薄暗い環境がよいとされています。
室温も良い睡眠をとるために重要なポイントです。
目安として夏は26〜28℃、冬は18〜22℃が快適な室温とされています。
就寝前のスマホ
就寝前のスマホは睡眠の質を下げてしまう原因となるといわれています。しかし、目覚ましのセットやお気に入りの曲を流したり、ストレス解消のために動画を見たりなど、就寝前でもスマホを触っているというケースが多いかと思います。
つまり、就寝前にスマホを触らないということは現代人にとって難しいかと思いますので、使い方のポイントを紹介します。
まず目や脳への刺激を少なくするためにブルーライトカット設定を使用し、画面の明るさも調整しましょう。
次に刺激的な動画や短いSNS動画の視聴、SNSでのインタラクティブな操作などは脳を興奮させてしまい、睡眠に影響を及ぼすため、行わないようにしましょう。
入眠習慣を持つ
入眠習慣とは、入眠をスムーズにするための寝る前の習慣を指します。
入眠習慣を持つことで、脳や身体にこれをやったら眠るという条件付けがなされ、スムーズな入眠の助けになります。
例えば、読書をしたり、癒される動画を見たり、ストレッチをしたり、アロマを嗅いだりなどがあります。
ぜひ自分に合った入眠習慣を持ってみてください。
無理に寝ようとしない
日によっては布団に入ってもなかなか寝付けないことがあったり、夜中に目が覚めてしまい再び寝付けないということがあるかと思います。
数回にわたってゆっくり深呼吸を繰り返すことで眠れることがありますが、どうしても眠れない時は、思い切って布団から出て気分転換するとよいです。
気分転換後に眠くなったら、また布団に入り眠りにつきましょう。
睡眠改善に役立つサプリメント
睡眠の質が低下し、朝バテがつらいという方には睡眠改善に役立つサプリメントがおすすめです。
睡眠薬といった医薬品とはことなり、サプリメントであれば副作用がほとんど無いため、体に負担をかけずに無理なく使用できます。
ストレスや加齢が原因で睡眠の質が低下している方や、ホルモンバランスの乱れによって不眠の症状が出ている方に向けて、睡眠改善に役立つサプリメントをいくつか紹介させてもらいます。
ストレス緩和と睡眠改善に役立つサプリメント
- 商品名
- スリープスターター(睡眠障害改善) 30パッチ
- 有効成分
- マグネシウム(リンゴ酸Mg) / カノコソウ根 / ホップ / 5-HTP / メラトニン
- 効果や特徴
-
スリープスターターの有効成分であるカノコソウ根やホップ花エキスはストレス緩和やリラックス効果がある天然ハーブで古くから不眠に用いられてきました。
また入眠をサポートし睡眠の質を向上させるといわれるマグネシウムや、睡眠サイクルを整え不眠を改善するメラトニン、セロトニンの前駆物質である5-HTPなどが配合されています。
スリープスターターは、貼るサプリメントとも呼ばれており、最新パッチ技術で迅速に限有効成分をとどけられるよう設計されています。 - 副作用
- 副作用は報告されていませんが、異常がある場合はただちに使用を止め、医師に相談してください。
- 商品名
- メラトニン5mg/10mg/20mg バイタルミー
- 有効成分
- メラトニン
- 効果や特徴
-
メラトニンは我々の脳の松果体で分泌されるホルモンで、睡眠や体内時計に深い関わりがあります。
メラトニンは夜になると分泌量が増えて自然な眠気を促し、朝になり光を浴びると分解されるため、睡眠のリズムを自然に改善するのに役立ちます。
またメラトニンは睡眠の他に体温、ホルモン分泌などサーカディアンリズム(概日リズム: 約24時間周期で変動する生体リズム)の調節に関わる重要なホルモンです。
加齢とともにメラトニンの分泌量は減少していくことがわかっているため、サプリメントで補っていくことで睡眠改善が期待できます。 - 副作用
- 得に副作用の報告はありませんが、稀に以下の副作用が出る場合があります。
日中の眠気、めまい、脱力感、気分の落ち込み、頭痛、食欲不振など
ホルモンバランスの乱れからくる睡眠障害の改善に役立つサプリメント
- 商品名
- ヒマラヤイブケア 生理前諸侯群(PMS)100%天然ハーブ
- 有効成分
- シャタヴァリ / マラバルナット / アショカツリー
- 効果や特徴
-
ヒマラヤイブケアは、インドの伝統医学であるアーユルヴェーダに基づいたサプリメントで女性特有のPMS(月経前症候群)、月経痛、更年期障害などの改善に役立ちます。
天然成分が豊富に含まれており、有効成分のシャタバリやマラバルナット、アショカツリーにはホルモンバランスの調整作用や月経痛、更年期障害の症状緩和の効果が期待できます。
インドの伝統医学であるアーユルヴェーダは、世界で最も歴史のある医療体系のひとつで、ヨガや呼吸法、数百種類のハーブを用いた食事慮法などで、心身の不調を整え病気を予防し、心と体の健康を保つことを目的としています。
医薬品のピルとは異なり、即効性は高くありませんが、副作用が非常に少ない点が女性にとってうれしいメリットです。 - 副作用
- 副作用は報告されていませんが、異常を感じた場合は使用を止め、医師に相談してください。
睡眠改善まとめ
今回は、睡眠の質の低下が原因で生じる朝バテについて解説してきました。
「朝から体がだるくて動く気がしない」「朝が一番疲れている」などといった方は満足な睡眠が取れておらず、朝バテが起きている可能性があります。
ご自身の睡眠を見直すことで、朝バテの解消や心身の不調の改善が見られるケースもあるため睡眠系サプリメントなどを活用して、無理なく睡眠リズムを整えていってください。
満足な睡眠をとれた翌日は、なんともいえない爽快感があります。
みなさんが健やかな日々を過ごせることを願っています。
Author
投稿者:ラククル管理人
ラククルのコラム・商品登録・サポートなど様々な業務を担当しております。ECサイトの運営は15年になります。これからもよろしくお願いいたします。